
【宅配デビュー戦】初めての積み込み現場は、静かな戦場だった
所属する委託会社も決まり、いよいよ宅配の仕事がスタートした。
言ってしまえば「宅配ドライバー1日目」──いわばデビュー戦だ。
初日は、なんと契約した会社の社長が直々に現場で指導してくれるとのこと。
正直ありがたいけど、ちょっと緊張もしていた。
朝、指定された営業所に到着。
まずは事務所に行って、受付の女性に一言。
「〇〇号車の端末ください」
返事はなかった。
……いや、正確には、無言で端末を手渡された。
あとで聞いた話によると、彼女は夜勤だったらしく、だいぶお疲れモード。
まあ、現場ではこういう無言コミュニケーションも“あるある”らしい。
端末を受け取って、荷物の積み込み場へ向かう。
すでに20人ほどの委託ドライバーたちが、それぞれ黙々と自分の車に荷物を積んでいた。
ピリッとした空気。
「ここに新入りが来ましたよ〜」なんて雰囲気は一切ない。
むしろ“誰も他人に構ってる暇なんてない”という感じ。
邪魔にならないよう、そっと車を端に停め、社長の到着を待つ。
10分後。
社長が現れレクチャーが始まった──。
社長のレクチャースタート:宅配1日の流れ
社長が到着して、いよいよ“宅配ドライバーの1日”が始まった。
まず教えられたのは、宅配業の全体的な流れ。
ざっくり言うと、こんな感じらしい。
■ 宅配1日の流れ
-
朝イチで営業所へ行く
営業所に到着。ここが戦いの始まり。(特に出勤時間の指定はないらしい) -
荷物を積み込む
自分の車に、今日配る荷物をどんどん積み込む。積み方次第で効率が大きく変わるらしい。(ここで下手に積むと後が大変だ) -
積み込みが終わったら現場へGO
自分の担当エリアまで移動。ここからが本番。 -
配達開始(時間指定は厳守)
積み込み時に地図にチェックした住所を確認して、効率のいいルートで配達を回る。
特に「午前指定」の荷物は、遅れるとクレームに直結するから注意! -
15時ぐらいに“ドッキング”
ここが宅配特有の用語。営業所や指定ポイントで、夕方〜夜指定の荷物を受け取る時間。 -
午後の部スタート
夕方以降に配達する荷物を積み込み、再び配達へ。だいたい20時くらいまで続く。 -
営業所へ帰還
配達が終わったら営業所に戻る。不在だった荷物を戻し、代引きで預かった現金を精算。 -
業務終了・帰宅
端末を返却して、ようやく一日の仕事が終わる。▽ 積み込みの基本ルール
① 大きな荷物はハッチバック側に
つまり後ろのドアに近い、取り出しやすい場所に積むということ。
重くて大きな荷物ほど、出し入れに手間がかかる。だからこそ、最もスムーズに出せる場所=ハッチバック側がベスト。
② 重いものは下、軽くて潰れやすいものは上に
これはもう積み込みの鉄則中の鉄則。
上下を間違えると、走行中の揺れでダンボールが潰れたり、中身が破損する可能性も。段ボールが「やめてくれ…」と泣く前に、重さでちゃんと順序をつけよう。
③ 前日の不在荷物も必ず積んでいく(再配達予約が入ってない場合)
たとえ予約が入ってなくても、いつ電話や連絡がくるか分からないのが宅配の現場。
その場で「今います!」の連絡が来て、荷物がない…では話にならない。必ず積んでおく、これが“できるドライバー”の備え
▽ さらに効率を上げるポイント
荷台の中をざっくり6分割して、エリア・住所ごとに分けて積む。
たとえば「〇〇町1丁目」「〇〇町2丁目」みたいにブロックごとに整理。
こうしておけば、現場で「あれ?あの荷物どこだっけ……」とならずに済む。
なん分割するかは自分の担当エリアや荷物の個数で決めるといいと思う。

▽ 積み込みが終わったら「地図マッピング」の作業
積み込みが完了したら、次にやるのが地図へのマッピング作業。
これは一日の配達ルートを組むための超重要ステップ。
① 荷札(伝票)を剥がして束にする
荷物にはそれぞれ伝票(荷札)が貼られている。
この伝票を荷物から剥がしてまとめておくのが最初の作業。
ポイントは「積み込むときに剥がすこと」。そうすることで、どこにどの荷物があるか把握しやすくなる。
ただし、伝票の種類が4種類あるので最初は混乱しがち。
「これは何の伝票?」「どっちが住所?」と戸惑うこともあるけど、これはもう慣れしかない。
② 地図にマジックでマッピング
伝票をすべて剥がし終えたら、次は地図に配達先の住所を書き込む作業へ。
自分の担当エリアの地図に、どこに何丁目の荷物があるかをマジックで書き込んでいく。
……ただこれ、地味に時間がかかる。
特に初心者の頃は、地図上で該当の住所を探すだけで一苦労。
「え、ここってどこ?」「同じ町名多すぎ!」と、ひとつの住所を見つけるのに5分以上かかることもザラ。でも、ここをテキトーにやると後で地獄を見る。
ルートがバラバラになり、何度も同じ道を行ったり来たり……
結果、時間はロスするし、体力もメンタルも削られていく。
▽ 使用する地図は「特別仕様」
使っている地図はちょっと工夫していて──
透明テープで全体をコーティングしてある。
こうすることで、マジックで直接書いても、あとでネイル用の除光液でサッと消せるんです。いわば、“自作ホワイトボード”みたいなもの。
これが意外と便利で、何度も書いては消す宅配の現場ではかなり重宝する。
ちなみに──
伝票を剥がすかどうかは、人によってやり方が違います。僕は最初、**「積み込みのときに伝票を剥がしてまとめておく」**ってやり方で教えられました。
地図にマッピングしやすいし、全体の流れも見渡せるので理にかなってるといえば理にかなってる。でも…
最終的に僕がたどり着いたスタイルは、**「伝票を剥がさない」**方式でした。理由はいろいろあるんですが──その話はまた別の機会に詳しく書こうと思います。
自分に合ったやり方を見つけるのも、この仕事の面白さのひとつです。
▽ 最後に「ルート組」で配達効率を最大化
地図へのマッピングが終わったら、いよいよルート組(ルート決め)のフェーズへ。
ここがしっかりできるかどうかで、配達の効率・スピード・疲労度がまるで違ってくる。
① 基本は「近い順・まとまったエリアから」
まず最初に考えるのは、どのエリアから回るか。
基本は「近場から」+「町ごとにまとまってる場所から」攻めていく。たとえば、「〇〇町1丁目 → 2丁目 → 3丁目」みたいに、流れを意識して順に回る。
逆に「遠い場所」「山の上」「時間指定がある荷物」などは、後回しにするか、タイミングを見て挟み込む。
② 時間指定の荷物は優先順位を上げる
「〇〇時までに配達」と指定されている荷物は、ルートの中でも最優先枠。
これを見落として組んでしまうと、あとで予定を崩されてバタつく羽目になる。先に伝票束から時間指定のものだけピックアップして、最初にルートに入れ込んでおくのがコツ。
③ 渋滞や道路事情も考慮に入れる
地図上では近くても、実際は一通・渋滞エリア・坂道多めなど、走ってみないとわからない罠もある。
このあたりは経験と試行錯誤で少しずつ“自分だけの最適ルート”が見えてくる。
④ ルートが決まったら、あとは突っ走るだけ
ある程度ルートが決まったら、あとは車に乗って走り出すだけ。
最初はミスや遠回りもあるけど、回数をこなせば確実にスピードと正確さが上がっていく。
▽ 補足:最初は完璧じゃなくてOK
配達のルート組って、実はパズルみたいなもん。
毎日荷物も違えば、エリアも変わる。
だからこそ、まずは「効率よりも確実に」届けることを優先。無理に急がず、地図と住所を照らし合わせながら、ひとつずつ落ち着いて配っていけば大丈夫。
▽ ルート確認が終わったら、いざ出発!
地図にマッピングして、ルートを組み終えたら──
最後にもう一度、時間指定の荷物や回る順番をざっくり頭に入れて、出発準備完了。忘れ物がないか、車のドアを閉める前にサッと確認するのが地味に大事。
ここまでで、配達前の準備はすべて完了です。
▽ まとめ:宅配の一日は準備で決まる
宅配の仕事は、実は「走り出す前」が勝負。
積み込み、伝票の処理、マッピング、ルート組み──
この準備の精度が高ければ高いほど、その日1日の動きがスムーズになる。最初は時間がかかって当然だけど、慣れてくると段取り力も上がる。
毎日少しずつ、自分なりのやり方をアップデートしていけばOK。
「準備で一日が決まる」
これは宅配ドライバーにとって、間違いなく真理です。次回は、実際の「配達中の流れ」や「現場でのあるある」についても書いていこうと思います。



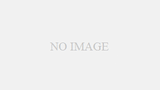
コメント