はじめに「NISA貧乏」という言葉をご存知ですか?
ここ数年、資産形成の一環としてつみたてNISAや新NISAを活用する人が急増しています。
特に2024年から始まった新NISA制度によって、年間360万円までの非課税枠が設けられ、投資を始めるハードルが一気に下がりました。
しかしその一方で、ネット上では「NISA貧乏」という言葉も目立つようになっています。
本来は将来の安心のために始めたはずの投資が、現在の生活を圧迫するケースも増えてきているのです。
「NISA貧乏」とは何か?
「NISA貧乏」とは、
つみたてNISAなどで毎月の投資額を捻出するために、日々の生活費が足りなくなってしまう状態
を指す俗語です。
SNSなどでは
-
「積立額を優先したら、生活費が赤字になった」
-
「貯金ゼロなのにNISAだけは継続している」
といった投稿が散見され、“将来のため”の行動が“現在の負担”になっている様子が見て取れます。
データから見るNISA利用の現状
上記から見ても、可処分所得の1〜2割を投資に充てている人が多いことがわかります。
適正なバランスであれば問題はありませんが、「余剰資金ではなく生活費を削っている」層が一定数存在することも事実です。
NISA貧乏に陥りやすい人の特徴
① 貯金がない状態で投資を始めた
「とにかく早く始めた方がいい」と言われることが多いNISAですが、生活防衛資金が不十分なまま投資を始めると、急な出費で資金ショートを起こす可能性があります。
② 家計の収支管理ができていない
毎月の固定費・変動費の把握が甘いと、「投資にいくら回してよいか」が判断できません。
③ 収入が増えていないのに投資額だけ増やしている
新NISAでは年間360万円まで積立可能になりましたが、投資額を増やせばいいというわけではありません。
生活費と投資額のバランス目安
以下のような支出配分が現実的とされます。
| 支出項目 | 目安割合 | 月収25万円の場合 |
|---|---|---|
| 生活費(家賃・光熱費・食費等) | 60〜70% | 15〜17.5万円 |
| 貯金 | 10〜15% | 2.5〜3.75万円 |
| 投資(NISA等) | 10〜15% | 2.5〜3.75万円 |
| 娯楽・その他 | 5〜10% | 1.25〜2.5万円 |
→ 投資は月収の10〜15%以内が無理なく続けられるラインとされます。
NISA貧乏を防ぐための3つの対策
① 生活防衛資金を先に確保する
最低でも「生活費3ヶ月分(目安:50万円〜100万円)」の現金貯金を優先しましょう。
これは投資よりも優先されるべき“生活の安全保障”です。
② 投資額を「定率」で管理する
手取りの10%程度からスタートし、余剰資金が増えた時にのみ増額するのが基本です。
初めから無理な設定をすると、生活に支障が出ます。
③ 副収入や固定費削減で“種銭”を増やす
支出を減らす/副業を始めるといったアプローチで、投資余力を確保する方法も効果的です。
投資と節約のパフォーマンス比較
| 行動 | 年間の効果 | コメント |
|---|---|---|
| 積立NISA(年利5%想定・年36万円) | 約1.8万円増 | 非課税効果ありだが即効性はない |
| 固定費削減(通信+保険) | 年4〜6万円削減 | 即効性あり/再現性も高い |
| サブスク解約・自炊など | 年3〜5万円削減 | 習慣化すれば強力な生活防衛策 |
まとめ|「NISAをやれば安心」ではない
-
投資は生活に余裕がある状態で行うことが大前提
-
積立額や運用成績だけでなく、現在の生活にどれだけ負担がかかっているかも考慮する
-
「投資しているのに生活が苦しい」と感じたら、それは家計バランスの再点検が必要なサイン
終わりに
「投資=意識高い」
「NISA=やらなきゃ損」
このような風潮は、間違ってはいません。
しかし一律に正しいとは限らないことも、冷静に理解しておくべきです。
あなたの家計と生活スタイルに合った「無理のない投資戦略」を設計しましょう。
NISAを活用して「未来の安心」を目指すなら、まず「今の安定」から始めてください。


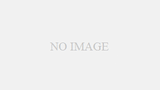
コメント