
はじめに:GW=遭難の季節って知ってた?
「せっかくのゴールデンウィークだし、自然に触れたいな」
「そういえば昔は登山とかしてたなぁ…ちょっと山でも行ってみるか」
──こんなふうに思った40代・50代のあなた。
その気持ち、めちゃくちゃわかります。自然と触れ合って、リフレッシュしたい。
でも、ちょっと待ってほしい。
実は、GWは1年で最も「登山遭難」が多いシーズンだって知ってましたか?
しかも最近は、中年層の遭難報告が目立つというデータもあるんです。
「昔は体力あったし」「このくらいの山なら大丈夫」──
その油断が、命取りになることもある。
今回は、**GWに登山遭難しやすい“中年男性のリアル”**と、
「どこの山で?なぜ?」という具体的な傾向をデータと共に紹介します。
GWの登山遭難、実は中年が目立っている【データあり】
警察庁が発表している「山岳遭難の統計データ(2023年度)」によると、
遭難者の年齢構成は以下の通り:
-
20代以下:15.2%
-
30代:13.4%
-
40代:18.7%
-
50代:22.1%
-
60代以上:30.6%
──つまり、中年層(40〜60代)が全体の70%近くを占めているということ。
とくにGW時期の事故件数を見ると、登山ブームに影響されて“復帰した中年”が要注意なのがわかります。
中年が遭難しやすい理由とは?
-
若い頃の成功体験に引きずられる:「昔はこの山、日帰りで余裕だった」
-
スマホ依存で紙地図・コンパスを持たない
-
装備をケチる:スニーカー、ノースリ装備、薄いペットボトル1本
-
“ソロ登山男子”が増加:誰にも相談せず、ルートも調べず、誰にも行き先を告げない
加えて、「ストレス発散したくて山に向かうけど、準備はめんどくさい」という矛盾があるんです。
どこの山で多い?GWの“中年遭難ホットスポット”3選
GW中に実際に遭難者が出ている山を紹介しつつ、「中年がハマりがちな罠」を解説します。
いずれも「日帰りで行ける」と誤解されやすい山ばかりです。
実際には、天候・混雑・登山者の集中で下山が遅れ、想定外の展開になることも。
実話:GW登山で道に迷った48歳の僕の体験
🧍♂️ 神奈川県在住 会社員 48歳
「GWに久々に高尾山へ登りました。午前は快晴で、気分よく山頂に到着。
下山ルートを変えて“冒険気分”で裏道に行ったのが大失敗。雨が急に降り出して滑る道で転倒。スマホも圏外。
人もまばらで不安になり、どの分岐かわからなくなってパニックに。1時間ほどウロウロして、結局大きな声で叫んだところを
通りがかった登山者が救ってくれました。マジで泣きました…。」
──よくある話ですが、「よくある=よく起こる」ってことなんです。
中年の登山、こうすれば安全にできる【チェックリスト】
「やっちまった」と後悔する前に。
これだけは守っておけば、“遭難リスク”はかなり下がります。
✅ 登山届 or 登山アプリで行き先を共有(YAMAP、コンパス推奨)
✅ 装備をケチらない:レインウェア・ヘッドライト・予備水分・笛・モバイルバッテリー
✅ 下山予定時刻+1時間で行動計画を組む
✅ 紙地図と方位磁石を最低限持つ
✅ 「何かあったら引き返す」判断力を事前に誓う
「引き返す勇気」は年齢を重ねた者にしか持てない最大の武器です。
ぶっちゃけ、中年の僕らは“遭難してもおかしくない”
GWの登山って、どこか「人生のリセットボタン」的に扱われがちなんですよね。
-
「仕事で疲れてるから自然で癒やされたい」
-
「久々に体動かしたい」
-
「人間関係に疲れて一人になりたい」
全部わかります。でも、それが**「思いつきソロ登山」→「遭難」ルート**に直結する場合もある。
そろそろ僕ら中年は気づかなきゃいけない。
若さを証明するための登山じゃなく、
無事に下山して家でビールを飲む登山が一番かっこいいってことを。
まとめ:登山は「挑戦」じゃなく「安全第一のレジャー」
-
GWは登山者・渋滞・気温変化・天候急変が重なるハイリスク期間
-
特に中年層は「無意識の自信過剰」が最大の敵
-
無理をしない。準備する。共有する。それが“遭難しないコツ”
僕自身、40代を過ぎてから「山に行く前の“準備の時間”」が好きになりました。
パッキングしながら、「あれ?なんか修学旅行の前夜みたいだな」って思うんです。
そうやって、ワクワクしながら、でも慎重に山に向かう──
その姿勢こそが、これからの中年に必要な“安全登山力”じゃないでしょうか?
では、みなさん。
無事に、帰ってきてください。


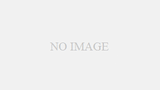
コメント