「またスマホを無駄に見てしまった…」
「買わなくてもいいものを買ってしまった」
そんな小さな後悔を、日常的に感じていませんか?
本書『満足できない脳』は、こうした“満たされない感覚”の原因が、私たちの脳の仕組みにあることを科学的に説明してくれる一冊です。著者はネバダ大学のマイケル・イースター教授。現代人の「もっと」「足りない」という渇望の正体を暴いていきます。
1. 私たちは「欠乏脳」でできている
“欠乏(けつぼう)”とは、単にモノが足りない状態ではありません。「自分には何かが足りていない」と感じている、心理的・主観的な不足状態を指します。
この欠乏感は、行動の原動力になります。
「もっと必要だ」「もっと得たい」と感じるたびに、人は何かに依存し、浪費し、繰り返し同じことを選ぶ──それが“欠乏脳”の正体です。
2. 欠乏ループを作る「3つの仕掛け」
- ① 機会:報酬を得られるチャンスがあるかどうか
- ② 変則的な報酬:当たるかどうかわからないスリル
- ③ 迅速な再現性:すぐにその行動ができてしまう環境
この3つがそろうと、人は理性よりも“本能”で動いてしまいます。
3. SNS・ネットショッピング・ガチャ──すべて欠乏ループ
著者が挙げる「欠乏ループ」の例は、驚くほど身近です。
- SNS:無限スクロール。次の投稿で“当たり”があるかもという期待。
- ネットショッピング:手軽さと“ワクワクする報酬”が合体。
- スマホゲーム:限定ガチャで“たまに”レアアイテムが出る。
- アルコール:飲む→人と会う→報酬がなければまた飲む。
このように、現代の生活は「欠乏を刺激する装置」に囲まれているのです。
4. 欠乏から抜け出す方法はあるのか?
著者は、「退屈と向き合うこと」「創造的な活動をすること」が欠乏ループから抜け出す鍵になるといいます。
- 🧠 自分の視野を広げる:旅行・登山・自然体験・読書など
- ✍️ 創造的な行動を選ぶ:文章を書く、音楽を作る、料理する
- 🕰 “何もない時間”に耐える:スマホ断ち・瞑想・ひとり時間
意識的に「報酬のない時間」を増やすことで、脳はリセットされやすくなります。
5. 欠乏ループは“自分だけ”じゃない
この本を読んで感じたのは、「欠乏感は誰にでもある」という当たり前のこと。
スマホやSNSを手放せないのも、浪費してしまうのも、“弱いから”ではなく、それが脳の仕組みによるものだということを理解することが大切です。
まとめ|「もっと欲しい」は脳が作る幻想かもしれない
もし今、満たされない気持ちに悩んでいるなら、それはあなただけじゃありません。
そして、それは「あなたのせい」ではなく「脳のクセ」かもしれません。
意識して、“不確実な報酬”から距離を取る。
その一歩が、自分らしさと満足感を取り戻す始まりです。
🔗 関連記事
- スマホ断ちで集中力が戻る|“思考の静寂”を取り戻す朝の習慣術
- 読書の効果がすごい|脳・感情・判断力が変わる自己投資術
- “いい人”をやめたいあなたへ】壊れた心を回復させる4つの心理アプローチ
- 許すのは“いい人”のためじゃない|怒りを手放し、自分の人生に集中する方法

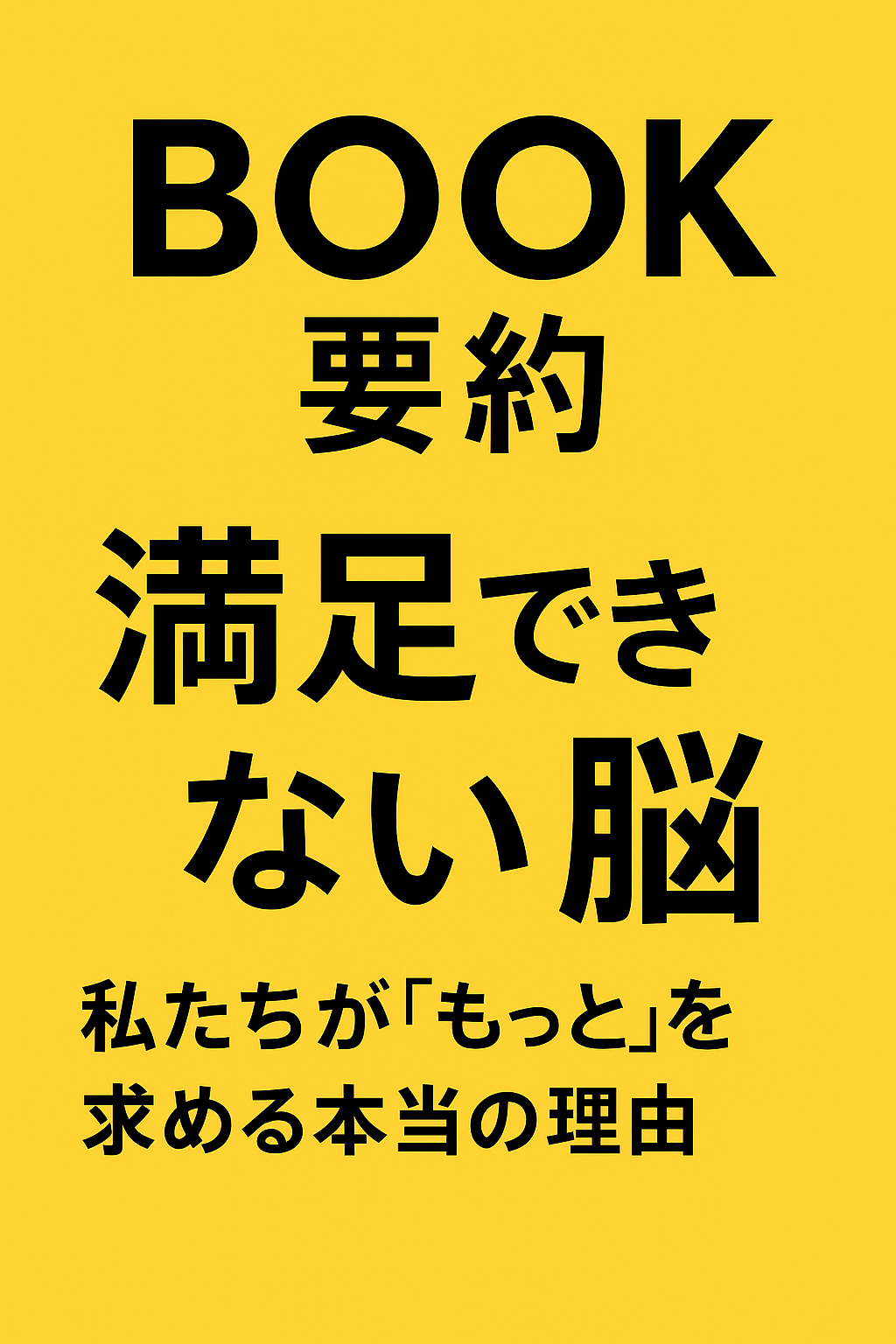
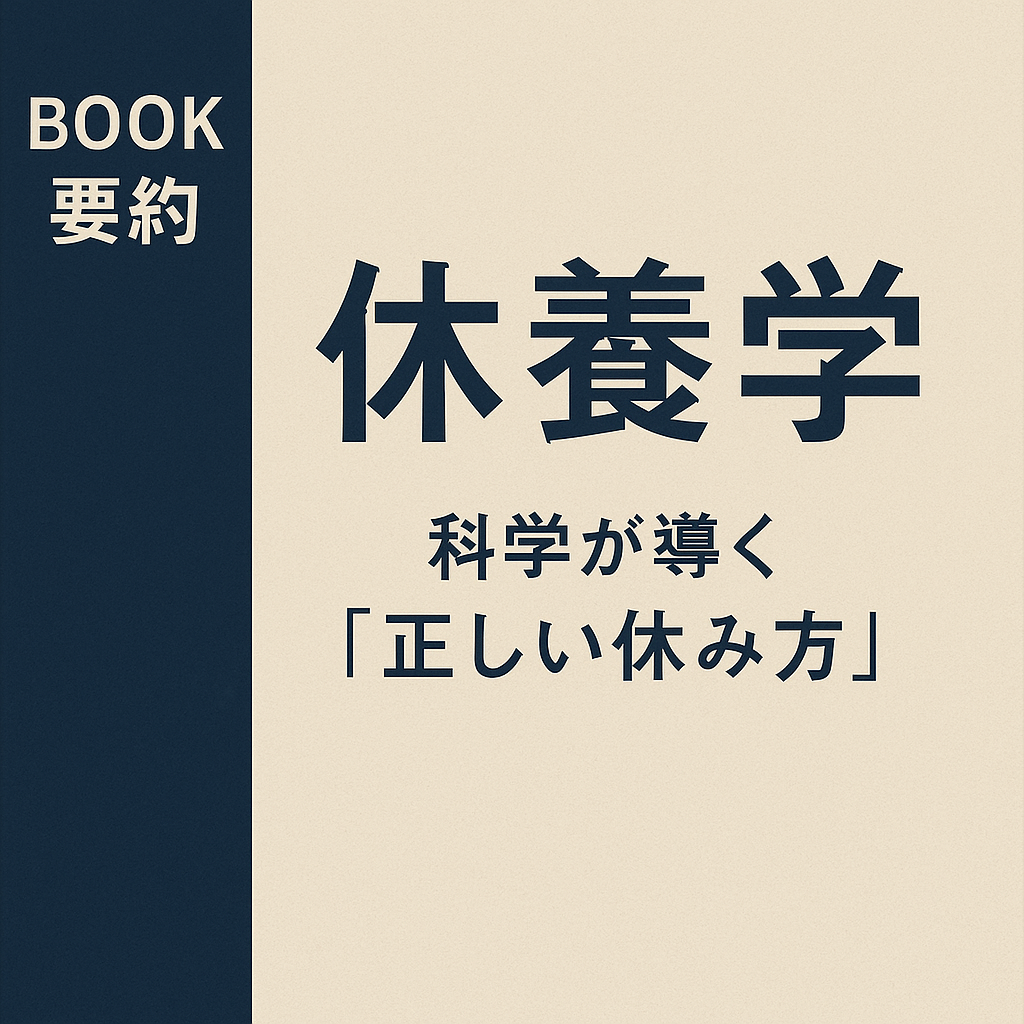
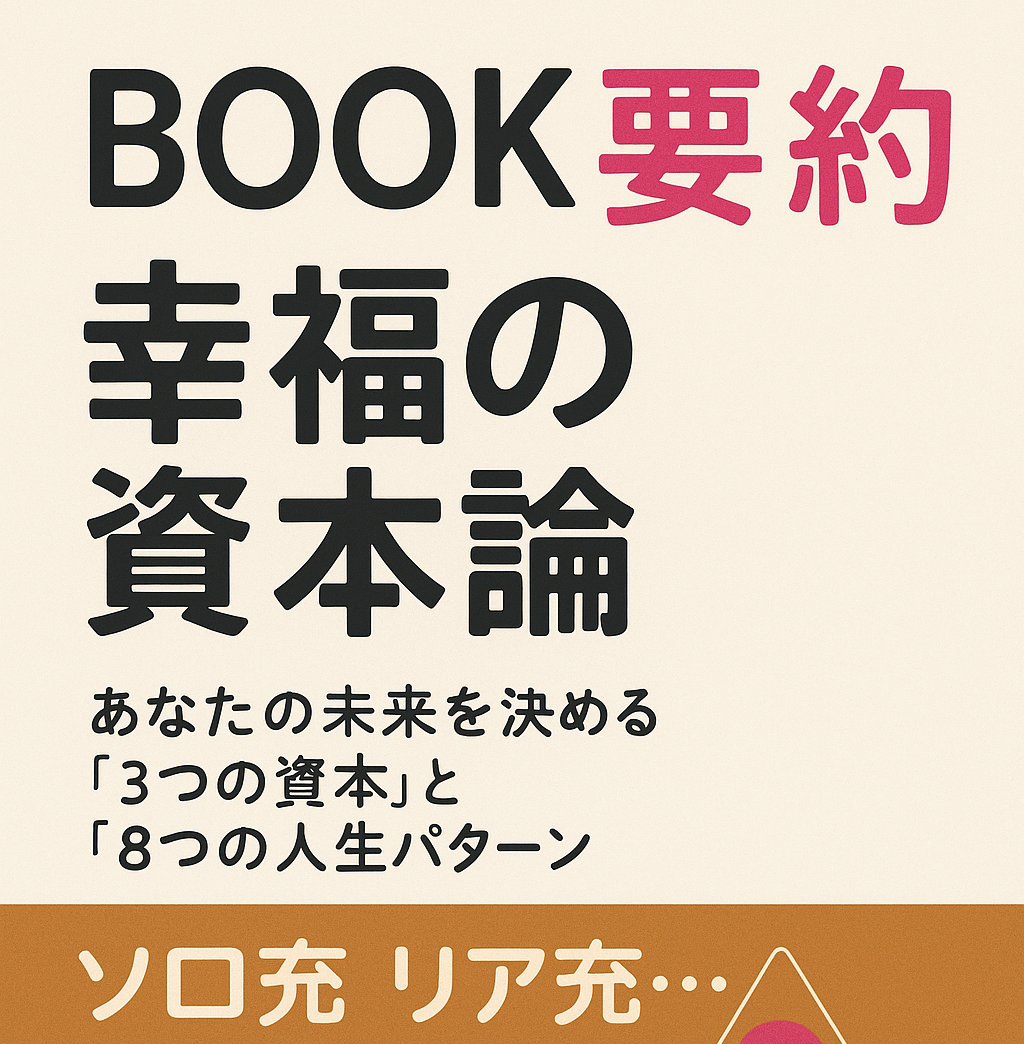
コメント