自分の人生に“なぜなぜ解析”を使ってみたら、驚くほど生きやすくなった話
「えっ、あの“トヨタの品質管理”が、悩み解決や感情整理に使えるの?」 そう思ったあなた。正解です。
会社員時代、イヤというほどやらされていた「なぜなぜ解析」。 トラブルが起きるたびに、「なぜ?」を5回繰り返して原因を追究させられたあの地獄の時間。 あれを思い出すと、胃のあたりがちょっと苦くなる。
でもその頃の経験が、まさかフリーランスになった今の自分の人生改善に役立つなんて── 正直、思ってもみなかった。
なぜなぜ解析って何だっけ?
「なぜなぜ解析」とは、 ある問題や現象に対して「なぜ?」を繰り返して、根本原因をあぶり出す手法。
もともとはトヨタ生産方式(TPS)で、製造現場の品質改善のために開発された。 創始者の一人・大野耐一氏はこう語ったとされる:
「なぜ?を5回繰り返せ。そうすれば真因が見えてくる。」
その考え方は、いまや製造業だけでなく、心理学・行動経済学・自己成長の分野でも使える“思考の掘削機”だ。
フリーランスになって、問題の「責任者」はすべて自分になった
会社を辞めて独立したとき、最初に感じたのは**“自由”と“不安”の混在**だった。
誰にも怒られない。 好きな時間に働ける。 けれど、売上が立たなければ即アウト。 誰のせいにもできない。
そんな中で、うまくいかないことがあると、つい感情的に嘆いていた。
「定期で契約してくれる業者がない…」
「メンタルが落ちる…」
「人間関係がしんどい…」
でもあるとき、ふと思った。
「これって、全部“なぜなぜ解析”すればいいんじゃないか?」
実際に“自分”に向かってなぜなぜしてみた
たとえば、ある月の売上が激減したとき。 当時の自分は、こう思っていた。
「今の時期は閑散期だししょうがない。運が悪かった。」
でもそれで終わらせていいのか? 自分自身に“なぜなぜ”してみた。
なぜ売上が減った?
→ 案件が来なかった
なぜ案件が来なかった?
→ エリア拡大の営業活動をしていなかった
なぜ営業してなかった?
→ エリア拡大する気が出なかった
なぜやる気が出なかった?
→ 前の案件でトラブルが重なって落ち込んでいた
なぜトラブルが起きた?
→ クライアントと最初に認識をすり合わせなかった
なぜすり合わせなかった?
→ 「面倒だし言いづらい」「いろいろ言われるし」と思ってスルーしていた
結果、売上が落ちた原因は「営業不足」ではなく、 自分の中にあるコミュニケーションの苦手意識だった。
僕は“なぜなぜ”を、毎日のジャーナリングに取り入れている
この“なぜなぜ解析”、僕は毎日のジャーナリングに組み込んでいる。
書くテーマはいつもシンプル。 「モヤモヤした」「焦った」「ダルかった」 そんな感情に“なぜ?”を重ねていく。
たとえば、
「今日はなんかダルかった」
→ なぜ? 昨晩スマホを長く見すぎた
→ なぜ見すぎた? 頭を切り替える気力がなかった
→ なぜ気力がなかった? ストレスが溜まってた
→ なぜストレス? 納期が詰まってた
→ なぜ詰まった? スケジュール立ててなかった
感情→行動→習慣→思考の癖へと、徐々に真因が見えてくる。
▶ なぜなぜジャーナリングの基本ステップ
その日の気になった感情を1つ選ぶ
「なぜ?」を3〜5回書き出す
最後に「じゃあどうすればいいか?」を一行で締める
こうすることで、ただの感情日記が人生の改善ノートになる。
原因はまさかの“そこ”?なぜなぜでわかった衝撃の真実
“なぜなぜ”をやっていると、本当の原因は意外なところにあると気づくことが多い。
たとえば、「気づいたら月末にお金が残っていない」と焦った日。
よくよく問いかけてみたら、こんな流れだった。
「なぜか財布にお金が残っていない」と感じた
→ なぜ1 毎日コンビニやスーパーでちょこちょこ使っていた
→ なぜ2 なぜ毎日コンビニやスーパーで買い物している?
→ なぜ3 まとめて買いものしないから余計なものを買ってしまう
→ なぜ4 毎食のメニューを考えながら買い物するのがめんどくさい
原因→毎日の食事メニューを考えるのがめんどくさいから
──まさか、そこかよ!
でもこれが、リアルな“根本原因”だったりする。
ちなみに僕の場合、この“根本原因”を解決したのは、おうちコープのような食材宅配サービスを使い始めたことだった。決まったセットが届くことで、毎回メニューを考えるストレスが減った。買い物に行く回数が減り、無駄な出費も減った。
逆に、メンタルが落ちる原因が、実は 「3日前にやらかした失敗をまだ引きずっていた」など、 感情の奥底に沈んでいた未処理のものだったりもする。
掘ってみなければわからない。
でも掘ったからこそ、同じ落とし穴にハマらずに済むようになる。
科学的に見ても「なぜなぜ」は理にかなっている
この“なぜなぜ解析”、心理学・脳科学の観点からも効果が認められている。
✅ メタ認知(Metacognition)
思考を客観視する力。学習効果・問題解決・自己理解に深く関与。
✅ 認知行動療法(CBT)
自動思考や信念のパターンに「なぜ?」と問いかけ、行動変容を促す。
✅ 行動経済学
判断ミスや習慣的選択の背景にある非合理性を、「なぜ」で特定する。
✅ マインドフルネス
「いまここ」の感情に気づき、「なぜそれを感じたのか?」と探ることで、 ストレスや不安の調整に効果を発揮。
まとめ:なぜなぜは、自分の“取扱説明書”をつくる作業
会社員時代に散々やらされていた「なぜなぜ解析」。 当時はただの義務だったけれど、
今ではそれが、自分の感情・行動・思考を理解する最強ツールになっている。
モヤモヤの正体が見えるようになる
習慣を改善できる
無駄な自己否定が減る
行動に納得感が出る
問題はいつも、「目に見えない場所」にある。
だからこそ、「なぜ?」と問いかける価値がある。
もしあなたが今、
何かに悩んでいるなら
前に進めない理由がわからないなら
同じことで何度もつまずいているなら
🔗 合わせて読みたい記事
- 困難を乗り越える戦略|“フィードバックモニタリング”という賢い習慣術
結果が出ない時、見直すべきは「やり方」ではなく「振り返りの仕組み」かもしれない。 - 時間投資エクササイズ|人生の“ROTI”を最大化せよ
時間の使い方を“見える化”し、投資リターンを高める思考トレーニング。 - 絶対やるな。──この“逆命令”が、あなたを動かす
禁止されたことほどやりたくなる」──心理的リアクタンスを行動に変える方法。


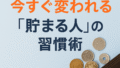

コメント